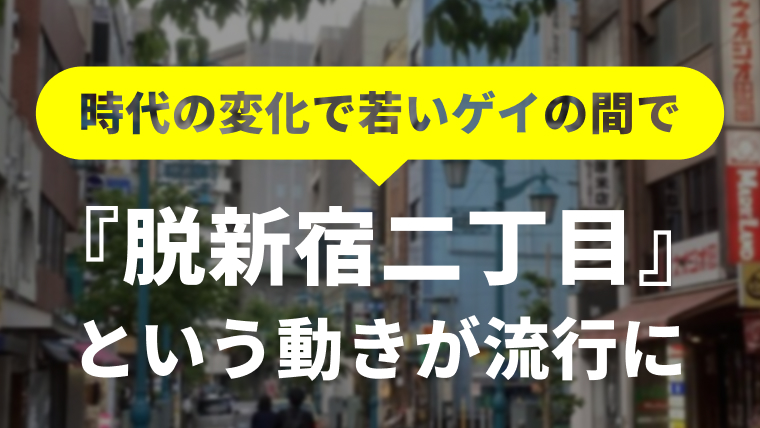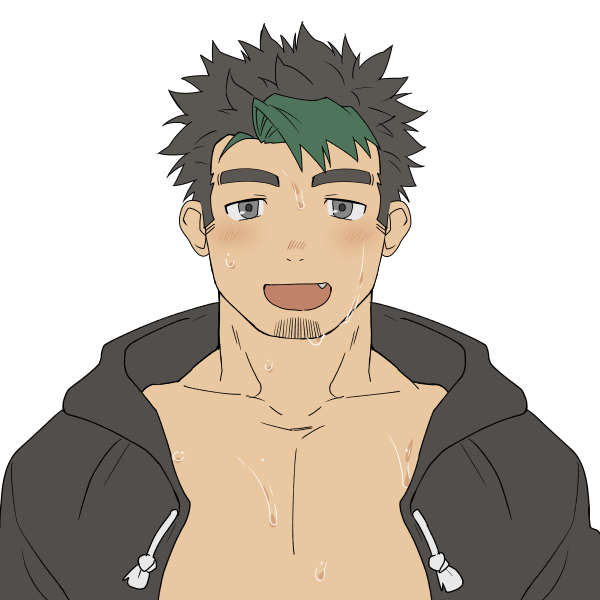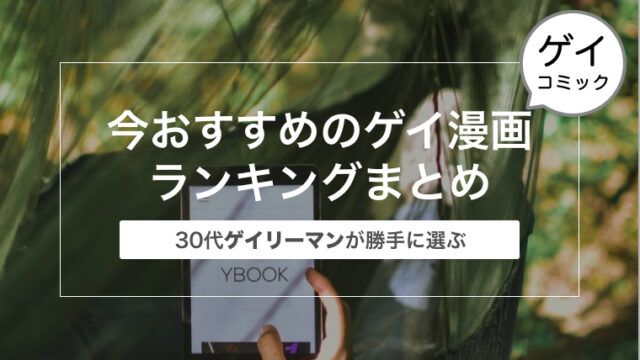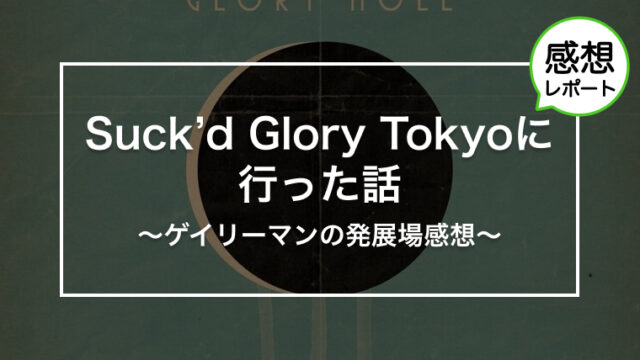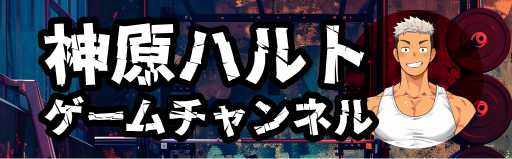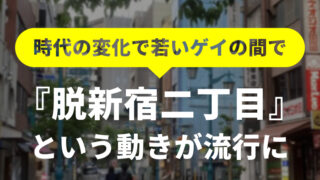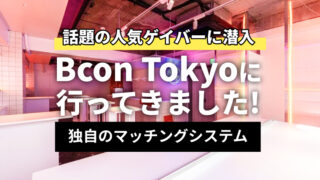かつてはゲイの出会いはインターネットを通じたものではなく、もっとアナログでした。ですが、ゲイは表だって「ゲイ」と公言する人は少なく出会いの場所は隠れた場所でした。
それが新宿二丁目をはじめとするゲイタウンです。
日本最大のゲイタウンである新宿二丁目でしたが、昨今その状況は変わりつつあります。若い世代を中心に「新宿二丁目に行かない・行かなくなった」という声が増えています。
この記事では、新宿二丁目離れの背景や、ゲイバー文化の変化について掘り下げていこうと思います。
そもそもなぜゲイタウンである新宿二丁目が生まれたのか

今は普通にゲイタウンとしてゲイバーやゲイクラブなどゲイスポットが多くある新宿二丁目エリアですが、なぜゲイタウンとして形成されたんでしょうか。
その歴史も深堀りしてみました。
江戸時代の宿場町、明治時代の遊郭という歴史的経緯から、遊郭などのそういったサービスを提供する場所としての土壌がありました。その後1958年に遊郭の跡地などは一般的な商売の場所としては使われることがほとんどなかったため、セクシャルマイノリティのお店、ゲイバーなどに利用されるようになりました。
社会的背景としては、多様な人々が集まる新宿という土地柄、比較的セクシャルマイノリティに寛容な雰囲気がありました。
1960年代以降のカウンターカルチャーの中心地として、自由な雰囲気が性的マイノリティの人々にとって居心地の良い場所となりました。
新宿駅の立地条件が良い為、各地からのアクセスが容易ででした。
全国にあるゲイタウンの多くは遊郭の跡地や、曰く付きの場所が多く、そのため普通住居としては避けられる場所が多いです。
昔、ゲイバーで飲んでるときに霊感がある人がゲイバーには霊が多いから気をつけないと…と言ってましたが実際にも曰く付きな土地柄も多いんですね。
ゲイバーの多くは窓がないことからも霊の逃げ道がない…と言われたりしますね!とはいえ僕もハスキーくんも霊感0です。(笑)
二丁目離れの主な要因
二丁目の高齢化とゲイバー文化の多様化

新宿二丁目のゲイバーは長年コミュニティの中心でしたが、常連客やママをはじめとしたスタッフの高齢化が進んでいます。
というのも新宿二丁目などのゲイタウンが全盛期だった頃は1980年代〜2000年前後なのでその当時20代だった人たちは40代以上になっています。
そのため新宿二丁目全体の高齢化は避けられません。
その結果、20代など若い世代のゲイにとっては会話のギャップも多い上に、自分がお客さんとして楽しみに行ってるのに会社のように気を遣わないといけない状況です。
その結果、若い世代が入りづらい雰囲気になり、新しい遊び場を求める動きが加速。
さらに最近では新宿二丁目に「わざわざ」行くよりも地元や近所で飲む人も多い上に若い世代が新橋・上野・中野・浅草など、他のエリアのゲイバーに分散しています。
わざわざゲイバーに行く人も減っていて、友達同士で集まって飲んだり、出会いを求めにわざわざ行かないという人も増えているようです。
最近20歳〜24歳くらいの子になぜ新宿二丁目に行かないの?と聞いても年上ばっかり、プロ、店子ばっかりという声も多いですね。
若者は別のスタイルを求めた結果ゲイバー離れが進む

「お酒を飲まない」「大人数より少人数の交流が好き」「マッチングアプリで出会えるからゲイバー、クラブに行く必要がない」といった価値観の変化していっています。
今は生活のスタイルだけでなくあらゆるものが情報化社会により多様化しています。
そのため出会いや休日の過ごし方などすべてが多様化しました。
出会いはアプリやSNSで充分で、共通の趣味を持つ友人が居たり、ゲイとの出会いは新たにゲイバーやクラブに行かなくてもいいという人が増えました。
その結果、そもそもゲイバー文化に馴染みがない世代が増えたことと、二丁目に限らずゲイバーそのものに足を運ぶ若者が減っています。
ゲイのためのゲイタウンじゃなくなった

ゲイのためのゲイタウンだった場所ですが、LGBTという言葉が一般に知られるようになってゲイの存在もかなり知られるようになりました。
メディアでの露出でも派手な格好で、派手な発言をするセクシャルマイノリティの方が増えてそれに伴ってゲイタウンに興味を持ついわゆるノンケの方もかなり増えました。
その結果、新宿二丁目には観光バーと呼ばれるゲイオンリーではなく女性でもノンケ男性でも入れるお店が増えました。
ですが、そのおかげでカミングアウトしてないからこそゲイバーで楽しめてた人にとっては肩身が狭くなってきました。
そうした流れからもゲイが減ってきています。インバウンドやノンケが楽しめる街になってきているようになりました。
日本ではまだまだゲイのカミングアウトは一般的ではありません。日本の歴史ある大企業であればあるほどそれは顕著です。
ゲイを差別はしないものの、腫れ物のように扱われることはあります。
二丁目は高いと感じるコスパの問題

ご存知の通り、世界的な戦争や円安、関税の影響で燃料費が高騰 し、日本でも食料品をはじめとする多くの商品が値上がりしています。さらに、社会保険料などの税負担も年々増加し、可処分所得は減少傾向にあります。
こうした経済状況の中で、若い世代はコスパ(コストパフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)を重視 する傾向が強まっています。そのため、「ゲイバーやゲイクラブはコスパが悪い」と感じる人も少なくありません。
実際、仲の良い友人同士でレンタルルームを借りて飲み会を開いたり、ホームパーティーやアウトドアで楽しんだりする人が増加しています。こうした選択肢のほうが気を遣わず、経済的にも合理的だと考えられているのです。
今後、日本の人口減少が進む中で税負担の増加や物価・光熱費の高騰は避けられない とされています。そのため、ゲイバーで数万円を使うよりも、将来のために貯蓄したい という考えが、バブルを経験していない若い世代の間で広がっているのかもしれません。
二丁目に行かない若者たちはどこへ?

では、新宿二丁目に行かなくなった若者たちは、どこで過ごしているのでしょうか?
近年、LGBTQ+に特化せず、気軽に友人同士で楽しめる 普通のバー・居酒屋・カフェを選ぶ人が増えています。また、オフ会やSNSで知り合った人と、ゲイタウンではない場所で遊ぶケースも一般的になりました。
さらに、マッチングアプリやオンラインでの交流が発展 したことで、ゲイバーを介さず直接出会えるようになり、ゲイバー離れを加速させています。
加えて、最近では繁華街から離れた場所に住む人も増加中。インバウンドの増加や外国人移住者の影響で、新宿・渋谷・池袋といった繁華街に住むことを避け、郊外に移る人が増えています。こうした流れの中で、地元のゲイバーを利用する人も増え、新宿二丁目に足を運ぶ必要がなくなってきているのです。
「脱新宿二丁目」は良いこと?悪いこと?

良いも悪いもお店側の視点か、お客さんの視点かで全然違います。
多様性の現代では選択肢が広がり、自分に合ったスタイルで楽しめる時代になったことが肯定的な部分です。
一方で否定的な意見としては新宿二丁目という「コミュニティの場」が衰退し、ゲイカルチャーが分散することで一体感が薄れていきます。そのほかゲイタウンというよりはゲイが接客する街という形になっていくでしょう。
将来的には二丁目に行く人と行かない人の間に文化や思想の断絶が生まれる可能性もあります。
まとめ:二丁目の未来と、これからのゲイカルチャー

結論から言うとこのまま日本では人口が減っていくことからも、新宿二丁目のゲイタウンとしての役割は完全に消えるわけではないが、かつての「絶対的な存在」ではなくなるかもしれない。
新宿二丁目に居るとほとんどのゲイが二丁目通いしているように感じるが、実は定期的にゲイバーに行く人は少数派という事実もあります。
今後イの遊び場や文化がより分散し、それぞれが好きなスタイルで楽しめる時代へ変化していくでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!Xアカウント(@Gay_husky)もあるのでよかったらフォローお願いします!
SNSでのシェアやコメントはお気軽に!クリックだけで応援につながるので「にほんブログ村」「人気ブログランキング」のクリックをお願いします!